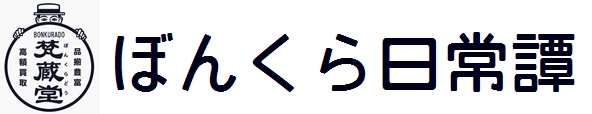会社を辞めて、祖父の店で古道具屋をやると報告した時、母は半ば怒ったような、そして半ば諦めたような口調で「好きにすれば」と言った。
蔵之介が勤める広告代理店『博通社』では、顧客が次々と不景気の波に飲み込まれていく中で、今年度中に大きな組織改編があるはずだと社内で囁かれていた。
現に、蔵之介のチームが担当している大手電機メーカーも、軒並み仕事が激減していた。
メーカー同士、不調な部署は縮小して飲み込まれ、好調な部署は拡大して合併し、そのたびにこちらまで競合他社と担当の座を争ってぶつかる羽目になる。
また、目まぐるしく変化する世の中に瞬時に対応するには、あまりにも組織が大きくなりすぎた。組織が大きすぎると前例や過去の成功談が壁となり、新しいことをひとつやり遂げるのに、必要以上の労力をかけなければならない。
上司に辞意を申し出ると、今まで辞める気配がなかっただけに、驚いた様子だった。
「死んだ祖父の店を継ぐため」と正しいような正しくないような理由をもっともらしく述べると、水面下で動いている10月の組織改編について教えてもらい、あっさりと9月末に退職することに決まった。
「これだと心に決めたら梃子でも動かねえって気でいてみろ、そうすりゃ周りが都合の良いように動くもんだ。」
祖父の持論だった。
「ただし、感謝の気持ちを忘れるな、蔵坊よ。自分のやることに最期まで責任を持て。最近の輩ってのは、感謝どころか人の所為、挙句の果てに責任の擦り付け合いだ。みっともないったらありゃしねえ。」
残念ながら感謝の気持ちとやらは祖母には伝わらなかったようだが、祖父が自分勝手で頑固なわりに人に囲まれて過ごしていたわけは、わかるような気がする。
蔵之介は五反田のマンションを引き払い、機能性よりもデザイン性で選んだ家具や家電やオシャレな家具は、必要なもの以外、売り払った。
霊園側の6畳間に運び込まれたダブルべッドも、古い台所に置かれたスタイリッシュな黒い冷蔵庫も、前の部屋では主役のように胸を張っていたのに、今では肩身が狭そうにしている。
反して、気紛れに買ったまま未使用だった木製のレコードプレーヤーが1階の8畳間に堂々と置かれていた。
12月。午後の5時を回ると外は既に薄暗い。
1月半ばの開店に向けての近所の挨拶もほとんど終わり、挨拶と交換のように貰ったお菓子や煮物などを並べて店先で一息ついていると、ゴウゴウと大きな音がして1台のトラックが店の前に止まった。
近所の人や通りすがりの人たちが興味深げに眺めている。
作業服姿の男たちが2人、トラックから滑り出ると、遅れて細身スーツの男が降りてきた。
「よおぉ、蔵ちゃん!」
男は、間口を広げるために入口のガラス戸を外す蔵之介に軽い足取りで歩み寄った。
「なんだ、風間も来たのか。」
業績好調なRE:KURAプロジェクト(※「登場人物紹介」参照)のプロジェクトリーダー、風間だった。同期入社で、調子が良く、上司にも受けがいい。
「おいおいおい、なんだってなんだ。同期の門出を祝おうってのに、随分なご挨拶だなあ!」
風間は蔵之介の肩をバシバシと叩くと、店を見上げた。
「へえ、中々洒落てる建物じゃないか。近くに谷中霊園っていう立地も良いよ。」
トラックの荷台から、片袖机、水屋箪笥、木製の棚などが次々と店先に運びこまれていく。古い家具には、現代のスタイリッシュなデザインの家具にはない、独特の渋みがある。
蔵之介が古道具の仕入先を探している時、風間から、蔵から出てくる古道具を買い取ってくれていた業者が不況で次々と倒産をしたため、古道具の処分に困っているという話を聞いた。そこで、その古道具を引き取る、という話を持ちかけたところ、話はトントン拍子に決まった。
「店に入りきらなかったら奥の納戸へ運んでください」蔵之介は作業服の男たちに声を投げ「風間は、ここらへんに詳しいのかい」と風間に向き直った。
風間は得意げに鼻を鳴らした。
「詳しくはないけど、多少勉強はしてるつもりだよ。蔵を再利用している事例を調べてたときにね、このあたりを散策したんだよ。ほら、もう少し先に古い蔵を利用したギャラリーがあるだろ?」
「スペース小倉屋さんか。」
「そうそう!他にもこの界隈は雰囲気のある建物がたくさんあるから、参考になるよ。いろんな土地に行ったけど、俺たちから見ればレトロで良い雰囲気だ、なんて思う建物でも、その土地の人から見れば、何が良いのかさっぱりわからん!てことは多いから。」
「地元の人からすれば、いつもある風景だって、とんでもなく有名な観光地になることだってある。そういう意味では、この土地は古くからここで商売をしている人と、新しくこの土地に惚れて商売を開いた人が、巧く支え合っているような気がするよ。」
風間は店の中に足を踏み入れると目を細めて店内を見回した。
「蔵ちゃんも、この土地に惚れて新しく商売するクチだな。」
蔵之介も後に続く。石油ストーブ独特の暖かさが冷えた身体を包みこむ。
「ああ、この土地と、この土地の人の人柄に・・・――。」
蔵之介の声が途切れた。
店から居間に上がる入口にひとりの女が座っている。
風間は不審げに蔵之介を見ると、その視線を辿った。
・・・あの女だった。
祖父の横に寄り添い、蔵之介の心に甘酸っぱい余韻を残した女。
あの時と同じ姿形のまま、艶やかな微笑みを浮かべて蔵之介を見ていた。
「嘘だろ・・・」
風間は女と蔵之介を交互に見比べると、口元を歪めるように笑った。
「おいおい、蔵ちゃん・・・、そんなに驚くことはないだろ。」
風間は女に近づくと、その隣に座って顎を持ち上げた。
大きな漆黒の瞳が風間を見上げる。
「おい風間・・・」
「大丈夫、かみつきゃしないって。おー、随分と気の強そうな美人顔だ。」
風間が顔を近づけると、女は厭そうに顔を顰めて、身体をくねらせるように立ち上がり、部屋の奥でまた座り込んだ。
「ああ、逃げられちゃった。」
風間は眉を下げると、固まっている蔵之介を見上げた。
「なんだよ蔵ちゃん、まるで幽霊でも見たみたいな顔してるぜ?」
よっ、と掛け声とともに立ち上がると、風間は、トラックへと戻る作業服の男たちに片手を上げた。懐から封筒を取り出し、蔵之介の目の前に掲げる。
「それじゃ、これ請求書ね。」
蔵之介のポケットに請求書を突っ込むと、風間は肩を軽く叩いて店を出た。
「蔵ちゃんが、そこまで猫嫌いとは思わなかった。それとも黒猫が通り過ぎると死者が出る、なんて迷信、信じてるクチかい?」
「・・・、・・・猫?」
「猫だろ?黒猫。」
風間は顎で女を示すと、女は真っ赤な舌をちらりとのぞかせて、鳴いた。
「・・・・・・ニャオン」
蔵之介が勤める広告代理店『博通社』では、顧客が次々と不景気の波に飲み込まれていく中で、今年度中に大きな組織改編があるはずだと社内で囁かれていた。
現に、蔵之介のチームが担当している大手電機メーカーも、軒並み仕事が激減していた。
メーカー同士、不調な部署は縮小して飲み込まれ、好調な部署は拡大して合併し、そのたびにこちらまで競合他社と担当の座を争ってぶつかる羽目になる。
また、目まぐるしく変化する世の中に瞬時に対応するには、あまりにも組織が大きくなりすぎた。組織が大きすぎると前例や過去の成功談が壁となり、新しいことをひとつやり遂げるのに、必要以上の労力をかけなければならない。
上司に辞意を申し出ると、今まで辞める気配がなかっただけに、驚いた様子だった。
「死んだ祖父の店を継ぐため」と正しいような正しくないような理由をもっともらしく述べると、水面下で動いている10月の組織改編について教えてもらい、あっさりと9月末に退職することに決まった。
「これだと心に決めたら梃子でも動かねえって気でいてみろ、そうすりゃ周りが都合の良いように動くもんだ。」
祖父の持論だった。
「ただし、感謝の気持ちを忘れるな、蔵坊よ。自分のやることに最期まで責任を持て。最近の輩ってのは、感謝どころか人の所為、挙句の果てに責任の擦り付け合いだ。みっともないったらありゃしねえ。」
残念ながら感謝の気持ちとやらは祖母には伝わらなかったようだが、祖父が自分勝手で頑固なわりに人に囲まれて過ごしていたわけは、わかるような気がする。
蔵之介は五反田のマンションを引き払い、機能性よりもデザイン性で選んだ家具や家電やオシャレな家具は、必要なもの以外、売り払った。
霊園側の6畳間に運び込まれたダブルべッドも、古い台所に置かれたスタイリッシュな黒い冷蔵庫も、前の部屋では主役のように胸を張っていたのに、今では肩身が狭そうにしている。
反して、気紛れに買ったまま未使用だった木製のレコードプレーヤーが1階の8畳間に堂々と置かれていた。
12月。午後の5時を回ると外は既に薄暗い。
1月半ばの開店に向けての近所の挨拶もほとんど終わり、挨拶と交換のように貰ったお菓子や煮物などを並べて店先で一息ついていると、ゴウゴウと大きな音がして1台のトラックが店の前に止まった。
近所の人や通りすがりの人たちが興味深げに眺めている。
作業服姿の男たちが2人、トラックから滑り出ると、遅れて細身スーツの男が降りてきた。
「よおぉ、蔵ちゃん!」
男は、間口を広げるために入口のガラス戸を外す蔵之介に軽い足取りで歩み寄った。
「なんだ、風間も来たのか。」
業績好調なRE:KURAプロジェクト(※「登場人物紹介」参照)のプロジェクトリーダー、風間だった。同期入社で、調子が良く、上司にも受けがいい。
「おいおいおい、なんだってなんだ。同期の門出を祝おうってのに、随分なご挨拶だなあ!」
風間は蔵之介の肩をバシバシと叩くと、店を見上げた。
「へえ、中々洒落てる建物じゃないか。近くに谷中霊園っていう立地も良いよ。」
トラックの荷台から、片袖机、水屋箪笥、木製の棚などが次々と店先に運びこまれていく。古い家具には、現代のスタイリッシュなデザインの家具にはない、独特の渋みがある。
蔵之介が古道具の仕入先を探している時、風間から、蔵から出てくる古道具を買い取ってくれていた業者が不況で次々と倒産をしたため、古道具の処分に困っているという話を聞いた。そこで、その古道具を引き取る、という話を持ちかけたところ、話はトントン拍子に決まった。
「店に入りきらなかったら奥の納戸へ運んでください」蔵之介は作業服の男たちに声を投げ「風間は、ここらへんに詳しいのかい」と風間に向き直った。
風間は得意げに鼻を鳴らした。
「詳しくはないけど、多少勉強はしてるつもりだよ。蔵を再利用している事例を調べてたときにね、このあたりを散策したんだよ。ほら、もう少し先に古い蔵を利用したギャラリーがあるだろ?」
「スペース小倉屋さんか。」
「そうそう!他にもこの界隈は雰囲気のある建物がたくさんあるから、参考になるよ。いろんな土地に行ったけど、俺たちから見ればレトロで良い雰囲気だ、なんて思う建物でも、その土地の人から見れば、何が良いのかさっぱりわからん!てことは多いから。」
「地元の人からすれば、いつもある風景だって、とんでもなく有名な観光地になることだってある。そういう意味では、この土地は古くからここで商売をしている人と、新しくこの土地に惚れて商売を開いた人が、巧く支え合っているような気がするよ。」
風間は店の中に足を踏み入れると目を細めて店内を見回した。
「蔵ちゃんも、この土地に惚れて新しく商売するクチだな。」
蔵之介も後に続く。石油ストーブ独特の暖かさが冷えた身体を包みこむ。
「ああ、この土地と、この土地の人の人柄に・・・――。」
蔵之介の声が途切れた。
店から居間に上がる入口にひとりの女が座っている。
風間は不審げに蔵之介を見ると、その視線を辿った。
・・・あの女だった。
祖父の横に寄り添い、蔵之介の心に甘酸っぱい余韻を残した女。
あの時と同じ姿形のまま、艶やかな微笑みを浮かべて蔵之介を見ていた。
「嘘だろ・・・」
風間は女と蔵之介を交互に見比べると、口元を歪めるように笑った。
「おいおい、蔵ちゃん・・・、そんなに驚くことはないだろ。」
風間は女に近づくと、その隣に座って顎を持ち上げた。
大きな漆黒の瞳が風間を見上げる。
「おい風間・・・」
「大丈夫、かみつきゃしないって。おー、随分と気の強そうな美人顔だ。」
風間が顔を近づけると、女は厭そうに顔を顰めて、身体をくねらせるように立ち上がり、部屋の奥でまた座り込んだ。
「ああ、逃げられちゃった。」
風間は眉を下げると、固まっている蔵之介を見上げた。
「なんだよ蔵ちゃん、まるで幽霊でも見たみたいな顔してるぜ?」
よっ、と掛け声とともに立ち上がると、風間は、トラックへと戻る作業服の男たちに片手を上げた。懐から封筒を取り出し、蔵之介の目の前に掲げる。
「それじゃ、これ請求書ね。」
蔵之介のポケットに請求書を突っ込むと、風間は肩を軽く叩いて店を出た。
「蔵ちゃんが、そこまで猫嫌いとは思わなかった。それとも黒猫が通り過ぎると死者が出る、なんて迷信、信じてるクチかい?」
「・・・、・・・猫?」
「猫だろ?黒猫。」
風間は顎で女を示すと、女は真っ赤な舌をちらりとのぞかせて、鳴いた。
「・・・・・・ニャオン」
スポンサードリンク