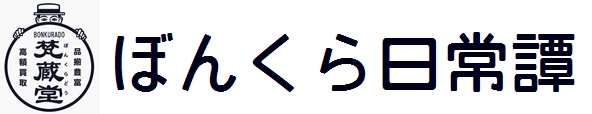母方の祖父が死んだ。
東大出身で珍しく英語が出来たため、当時花形の財閥系総合商社に入社。
50代前半で執行役員にまで上り詰めた挙句、唐突に「古道具屋をやる」と辞めた男である。
あまりの自分勝手さに、箱入り娘であった祖母はついていけず、とうとう家を飛び出した。
飛び出した先は娘夫婦の家。つまり、蔵之介のマンションである。
小学生だった蔵之介は、母と祖母、大人2人がリビングで泣いているのを見て、何か大変な事件に遭遇してしまったような気分になったのを今でも覚えている。
そして子供ながらに、居場所がなさそうに経済新聞を読んでいた父の姿に同情したものだった。
祖父は家事全般も難なくこなしていたようで――祖母は誰か世話をしてくれる好い人でも居るに違いないと言い張っていたが――結局、迎えに来ることはなかった。
祖母はそれからずっと家にいて、もう夫婦の関係ではないと聞いたのは、小学校を卒業した頃だった。
祖父の古道具屋は台東区の谷中にあった。
霊園のすぐそばにあり、興味本位で見に行くのはなんだか気が引けた。
ただ、一度だけ、中学の頃に家族に黙って祖父の店を訪ねたことがある。
その時、どぎまぎするほど艶やかな若い女が居て、「おじいちゃんの新しい恋人?」と聞くと、祖父は驚いた顔をした後、ニヤニヤと笑って「そうだ、羨ましいだろう。」と笑った。
女も笑っていた。その顔があまりにも色っぽくて腰のあたりがウズウズとした…という記憶は、羞恥心と共に胸の奥に残っている。
祖父は背も高いし、彫りも深く、なによりオシャレだった。
夏は白絣にカンカン帽、冬は三つ揃いに中折れ帽のスタイルがよく似合う。
独り身ともなれば、多少色のある話も出てくるだろう。
蔵之介はふと思った。
彼女は、祖父が死んだのを、知っているのだろうか。
葬式は身内だけで執り行われ、孫の蔵之介と娘夫婦である父と母、あとは数人の親戚に見送られ、祖父は荼毘に付した。
「勝手に生きて、勝手に死んで、良い人生よね。」
立ち上る煙を見て、ぽつりと呟いた母の言葉が、今も耳に奥に残っている。
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
「もし売りに出されるなら、この建物はそのままの方がいいかもしれませんね。」
よく通る声が、記憶の海に沈んでいく蔵之介の意識を引き上げた。
20年の時を経て、蔵之介は祖父の店を訪れている。
主を失った建物は、心なしか寂しげで、どんよりとしていた。
よく磨かれた古道具の棚には永井荷風の本が並んでいる。
祖父の心の師匠だと、昔訪ねた日の帰り際に本を貰ったが、結局読まずじまいだ。
「こんな古い家が…?」
「ええ、貸してもいいかもしれません。」
白澤不動産――この辺り中心とした物件を扱う不動産屋で、祖父がこの物件を買い取ったときに世話になったという。今は息子が後を継いだようだ。
世代違えてまた世話になるというのは、どことなく親近感が湧く。
「墓場の近くで、築100年に近い物件なんて、借りる人いるんですかね。」
「谷中霊園は墓場というより公園に近い雰囲気ですから。春は桜も綺麗ですし。それに最近…ここ10年ぐらいですかね、この界隈で古い物件を探している若い方、多いんですよ。」
そういえば、蔵之介が在籍している広告代理店でも、地方自治体と連携し、蔵を改築して、地域の目玉になるレストランやカフェ、ホールなどをプロデュースしていく【RE:KURAプロジェクト】が好調だと言う。
この界隈は23区内にしては、のんびりとした空気が流れていて、古い建物が残された風景も心地よい。目まぐるしい時間の流れから離れて自分を見つめ直す時間を求める人が多くなっているのかもしれない。
蔵之介も入社以来、立ち止まることなく押し寄せる仕事の波を千切っては投げ整えては崩しと休みなく働いてきたが、久し振りに時間がゆっくりと流れている気がする。
「それに、古道具の金鳳亭(きんぽうてい)といえばガイドブックには必ず載るお店ですから、元金鳳亭となれば、すぐに借り手がつくと思いますよ。」
永井荷風が“断腸花(だんちょうか)”という気に入りの花から自らの家を【断腸亭】と名付けたというエピソードを真似て、庭に咲いていた金鳳花(きんぽうげ)から【金鳳亭】と名付けたという。
ここらへんのくだりは、白澤氏から得た知識だ。
「もし改装云々でお金をかけたくなければ、古道具付きの現状引き渡しでも全く問題ないと思います。」
店先から8畳ほどの畳の部屋に上がると、縁側から猫の額ほどの庭が一望できる。
年季の入った青緑色の物干し竿には、薄汚れたタオルがぶら下がっていた。
「夏なのに、涼しいですね。」
「ええ、昔の家は風通し良く造られていますから、冷房は絶対につけない、とおっしゃっていたんです。冬はストーブを焚けば越えられますからね。でも5年くらい前かな、猛暑が続いたでしょう?うちの父に“折角客が増え始めたんだから、せめて店の方にだけつけた方がいい”なんて言われてしぶしぶクーラーをつけられたんですよ。」
周りにいたのは家族ではなかったが、祖父は決して孤独ではなかったようだ。
家族と一緒に暮らしながらも、最後まで祖父を恨んでいた祖母の方が、よほど孤独だったのかもしれない。
今更ながら、祖母とあまり言葉をかわそうとしなかったことを後悔した。
元々名家だった祖母の遺産が入ると、両親は都心のマンションを売り払い、静岡に農園付きの家を買って移り住んだ。父は定年退職した日、母から、別れるか静岡に家を買うかという究極の選択を突きつけられたようだ。
結局母は“この世で一番嫌いな人”と称する祖父に似た性格をしている。
一度それを指摘したとき、林檎が飛んできて危うく鼻の骨を折るところだったので、その件については触れないことにしていた。
この店の件で白澤氏が母に連絡したときも「あんな店、煮るなり焼くなり好きにして」と取り付く島がなかったようで、そうはいっても人の家を勝手に売りさばくわけにもいかず、ようやくのことで蔵之介に辿り着いたという。
奥に進むと台所があり、その横は風呂場になっていた。
階段は急で、80過ぎの老人が住んでいたとは思えない造りだ。
「金鳳亭さんは本当に若々しくて。こんな階段も軽い足取りで上がっていたんじゃないかと思うほどです。」
白澤氏は祖父を“金鳳亭さん”と呼ぶ。売れない落語家のようで可笑しかったが、その響きにはぬくもりがあった。
ギシギシと軋む階段を上がると、和室が3間。閉め切られた2階はムッとした熱気が籠っている。3間を仕切る襖を開き、雨戸を外して全ての窓を開けると、涼しい風が一気に通り抜けて行った。
通りに面した10畳の部屋は、祖父の書斎のようで、書庫よろしくたくさんの本棚が並んでいた。
祖父の心の師匠である永井荷風はもちろん、夏目漱石、森鴎外、坪内逍遥などの文学作品、江戸川乱歩や横溝正史に、エドガー・アラン・ポーやアガサ・クリスティーなどのミステリー小説も多い。
窓に面して置かれた存在感のある文机の上には、何冊もの原稿用紙と本が重ねられていた。
「小説でも書いていたんですかね。」
「いやあ…、そういう話は聞いたことがないですけどね。でも自叙伝でも書いたらどうですかって進めたことはありますよ。人様に見てもらうような人生じゃないって笑っていましたけど。」
蔵之介は、丸い煎餅布団の上に胡坐をかき、傍に転がっていた万年筆を拾い上げた。
開いた窓から雲ひとつない青空が広がっている。
ザワザワとした木々の擦れる音を聞きながら、生き急ぐように駆け抜けてきた日々が頭の中に浮かんでは消えた。
何を目指すわけでもなく、ただひたすら、滝の如く流れ落ちる時間を受け入れる毎日。
休み少なく働き、金を稼ぎ、比較的良いマンションに住んで、車も買った。
ときどきの休みはどこに行く気もせず、合コンで知り合った女から来たメールを思い出したように返してみる。
出逢いがないわけではない。何度か食事をするうちに深い付き合いに発展することはよくあった。
だが、急な仕事でデートを直前キャンセルする羽目になり振られることもよくあった。
・・・それが、蔵之介の日常だった。
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
「あ、明地あけちさん。」
不意に声がして我に返ると、窓際に立っていた白澤氏が窓から身を乗り出していた。
「ああ、白澤さん。……――あら。」
蔵之介が白澤氏の横から顔を出すと、窓の下にいた淡い紫色の着物を着た女性は、驚いたように日傘を下ろし、軽く頭を下げた。蔵之介も釣られるように頭を下げる。
「富士見坂にある“ふじみ荘”の大家さんです。この近くのご自宅で着付け教室をなさっているんですよ。」
白澤氏は口早に紹介すると「金鳳亭さんのお孫さんです。」と窓の下にも伝えた。
明地と呼ばれた女性はさらに驚いたように口に手を当て、今度は深々と頭を下げた。
「それは・・・、ご愁傷様でした。金鳳亭さんには色々とお世話になりまして。」
「いえ、こちらこそ祖父がお世話になりまして。」
蔵之介が身を乗り出すようにして返すと、明地夫人はしばらく眩しそうに蔵之助を見上げていたが、「嗚呼、金鳳亭さんと、よく似ていらっしゃるわ。」と静かに笑った。
「では白澤さん、あとで…15時過ぎるけれど、お伺いするから。」
「ええ、お待ちしております。」
明地夫人は着物によく似合う真っ白な日傘を差すと、カランコロンと軽やかな音を立てて遠ざかって行った。その姿が角を曲がると、白澤氏は窓を閉めた。風が止まるだけで温度が急に上がったように感じる。
「富士見坂というのは、富士山が見えるんですか?」
「ええ、今はマンションが建ってしまって半分ほど見えなくなっているんですが、冬の朝は特に綺麗に見えますよ。」
蔵之介は万年筆を机の上に置いた。『F坂の殺人』と見たことがあるようなタイトルが原稿用紙に殴り書きされている。
「“ふじみ荘”もかなり古い物件で、明地さんのご主人がご存命のときに、建て替えの話も出たんですが、安く借りたい人もいるだろうということで今もそのままなんです。」
「ああ、今はお独りなんですか?昔はさぞかし美人だったんでしょうね。あ、いや今も美人ですけど。」
軋む階段を降りながら蔵之介が言うと、白澤氏はわざとらしく声を潜めた。
「明地さんって・・・父の初恋の人なんです。」
不動産屋に着いた時、最初に対応してくれた年配の男の顔が思い浮かぶ。
白澤氏は笑いを含む口調で続けた。
「ご主人が亡くなる前はほとんど関わりなかったんですが、お独りになってからはご自身で動かざるをえないので、うちにも頻繁に来るようになったんです。
だから、明地さんが来る日には、必ず父は店にいるんですよね、お気に入りのネクタイをつけて。」
蔵之介は笑った。
「ああ、だから今日も店にいらっしゃったんですね。まあ、初恋っていうのは、実らないからこそ、いつまでも甘い思い出ですから。」
・・・初恋。
あの女の艶かしい笑顔が思い出される。祖父と一緒に柱の影からひょいと顔を出しそうで、思わず部屋の中を見回すと、年代物の柱時計が目に入った。ここを訪れてもう1時間も経っている。
釣られて時計を見上げた白澤氏は慌てて自分の腕時計を覗き込んだ。
「ああ、もうこんな時間ですね。お忙しいのにすいません。」
「いやいや、久し振りにゆっくり過ごせました。20年振りに祖父に歩み寄れたような気がして楽しかったです。」
店先のガラス戸から見える外は、うんざりするほど良い天気だ。
蝉の大合唱に、駆け回る子供たちの甲高い笑い声が響いた。
「では、ご検討いただいて・・・」
言いかける白澤氏を制するように、蔵之介は首を振った。
「もう決めました。白澤さんには長い時間お付き合い頂いたのに申し訳ないんですが…。」
白澤氏は蔵之介の言葉を理解しようと、何度か目を瞬いた。
「と、おっしゃいますと・・・?」
「誰にも売らず貸さず。この店で、古道具屋をやろうと思います。」
蔵之介は、声を失う白澤氏の横を通り、店に下りると、並んだ古道具を眺めた。
白澤氏はしばらく固まっていたが、やがて嬉しそうに笑みを零すと、蔵之介の後を追って古道具の前に並んだ。
「古道具の金鳳亭復活ですか?」
「いや、祖父のやり方を引き継げるわけじゃないから、店の名前も変えようと思います。そうだなぁ・・・――蔵之介からクラをとって、古道具のボンクラ堂とか。」
20年前のあの日、祖父に将来の夢を聞かれた蔵之介は「良い大学にいって、良い会社に就職する」と答えた。
すると祖父は「将来の夢がそんなチッポケとは、とんだボンクラだよ。蔵坊のクラはボンクラのクラに違いねえ」と呆れたように言った。
店の名前に、白澤氏は笑った。
「ボンクラって言葉、金鳳亭さん、よく使ってましたね。」
「口は悪いですからね、愛情のある罵倒ってやつかと。」
――ニャオン・・・
蔵之介の言葉に賛成したように、どこかで猫の鳴き声がした。
東大出身で珍しく英語が出来たため、当時花形の財閥系総合商社に入社。
50代前半で執行役員にまで上り詰めた挙句、唐突に「古道具屋をやる」と辞めた男である。
あまりの自分勝手さに、箱入り娘であった祖母はついていけず、とうとう家を飛び出した。
飛び出した先は娘夫婦の家。つまり、蔵之介のマンションである。
小学生だった蔵之介は、母と祖母、大人2人がリビングで泣いているのを見て、何か大変な事件に遭遇してしまったような気分になったのを今でも覚えている。
そして子供ながらに、居場所がなさそうに経済新聞を読んでいた父の姿に同情したものだった。
祖父は家事全般も難なくこなしていたようで――祖母は誰か世話をしてくれる好い人でも居るに違いないと言い張っていたが――結局、迎えに来ることはなかった。
祖母はそれからずっと家にいて、もう夫婦の関係ではないと聞いたのは、小学校を卒業した頃だった。
祖父の古道具屋は台東区の谷中にあった。
霊園のすぐそばにあり、興味本位で見に行くのはなんだか気が引けた。
ただ、一度だけ、中学の頃に家族に黙って祖父の店を訪ねたことがある。
その時、どぎまぎするほど艶やかな若い女が居て、「おじいちゃんの新しい恋人?」と聞くと、祖父は驚いた顔をした後、ニヤニヤと笑って「そうだ、羨ましいだろう。」と笑った。
女も笑っていた。その顔があまりにも色っぽくて腰のあたりがウズウズとした…という記憶は、羞恥心と共に胸の奥に残っている。
祖父は背も高いし、彫りも深く、なによりオシャレだった。
夏は白絣にカンカン帽、冬は三つ揃いに中折れ帽のスタイルがよく似合う。
独り身ともなれば、多少色のある話も出てくるだろう。
蔵之介はふと思った。
彼女は、祖父が死んだのを、知っているのだろうか。
葬式は身内だけで執り行われ、孫の蔵之介と娘夫婦である父と母、あとは数人の親戚に見送られ、祖父は荼毘に付した。
「勝手に生きて、勝手に死んで、良い人生よね。」
立ち上る煙を見て、ぽつりと呟いた母の言葉が、今も耳に奥に残っている。
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
「もし売りに出されるなら、この建物はそのままの方がいいかもしれませんね。」
よく通る声が、記憶の海に沈んでいく蔵之介の意識を引き上げた。
20年の時を経て、蔵之介は祖父の店を訪れている。
主を失った建物は、心なしか寂しげで、どんよりとしていた。
よく磨かれた古道具の棚には永井荷風の本が並んでいる。
祖父の心の師匠だと、昔訪ねた日の帰り際に本を貰ったが、結局読まずじまいだ。
「こんな古い家が…?」
「ええ、貸してもいいかもしれません。」
白澤不動産――この辺り中心とした物件を扱う不動産屋で、祖父がこの物件を買い取ったときに世話になったという。今は息子が後を継いだようだ。
世代違えてまた世話になるというのは、どことなく親近感が湧く。
「墓場の近くで、築100年に近い物件なんて、借りる人いるんですかね。」
「谷中霊園は墓場というより公園に近い雰囲気ですから。春は桜も綺麗ですし。それに最近…ここ10年ぐらいですかね、この界隈で古い物件を探している若い方、多いんですよ。」
そういえば、蔵之介が在籍している広告代理店でも、地方自治体と連携し、蔵を改築して、地域の目玉になるレストランやカフェ、ホールなどをプロデュースしていく【RE:KURAプロジェクト】が好調だと言う。
この界隈は23区内にしては、のんびりとした空気が流れていて、古い建物が残された風景も心地よい。目まぐるしい時間の流れから離れて自分を見つめ直す時間を求める人が多くなっているのかもしれない。
蔵之介も入社以来、立ち止まることなく押し寄せる仕事の波を千切っては投げ整えては崩しと休みなく働いてきたが、久し振りに時間がゆっくりと流れている気がする。
「それに、古道具の金鳳亭(きんぽうてい)といえばガイドブックには必ず載るお店ですから、元金鳳亭となれば、すぐに借り手がつくと思いますよ。」
永井荷風が“断腸花(だんちょうか)”という気に入りの花から自らの家を【断腸亭】と名付けたというエピソードを真似て、庭に咲いていた金鳳花(きんぽうげ)から【金鳳亭】と名付けたという。
ここらへんのくだりは、白澤氏から得た知識だ。
「もし改装云々でお金をかけたくなければ、古道具付きの現状引き渡しでも全く問題ないと思います。」
店先から8畳ほどの畳の部屋に上がると、縁側から猫の額ほどの庭が一望できる。
年季の入った青緑色の物干し竿には、薄汚れたタオルがぶら下がっていた。
「夏なのに、涼しいですね。」
「ええ、昔の家は風通し良く造られていますから、冷房は絶対につけない、とおっしゃっていたんです。冬はストーブを焚けば越えられますからね。でも5年くらい前かな、猛暑が続いたでしょう?うちの父に“折角客が増え始めたんだから、せめて店の方にだけつけた方がいい”なんて言われてしぶしぶクーラーをつけられたんですよ。」
周りにいたのは家族ではなかったが、祖父は決して孤独ではなかったようだ。
家族と一緒に暮らしながらも、最後まで祖父を恨んでいた祖母の方が、よほど孤独だったのかもしれない。
今更ながら、祖母とあまり言葉をかわそうとしなかったことを後悔した。
元々名家だった祖母の遺産が入ると、両親は都心のマンションを売り払い、静岡に農園付きの家を買って移り住んだ。父は定年退職した日、母から、別れるか静岡に家を買うかという究極の選択を突きつけられたようだ。
結局母は“この世で一番嫌いな人”と称する祖父に似た性格をしている。
一度それを指摘したとき、林檎が飛んできて危うく鼻の骨を折るところだったので、その件については触れないことにしていた。
この店の件で白澤氏が母に連絡したときも「あんな店、煮るなり焼くなり好きにして」と取り付く島がなかったようで、そうはいっても人の家を勝手に売りさばくわけにもいかず、ようやくのことで蔵之介に辿り着いたという。
奥に進むと台所があり、その横は風呂場になっていた。
階段は急で、80過ぎの老人が住んでいたとは思えない造りだ。
「金鳳亭さんは本当に若々しくて。こんな階段も軽い足取りで上がっていたんじゃないかと思うほどです。」
白澤氏は祖父を“金鳳亭さん”と呼ぶ。売れない落語家のようで可笑しかったが、その響きにはぬくもりがあった。
ギシギシと軋む階段を上がると、和室が3間。閉め切られた2階はムッとした熱気が籠っている。3間を仕切る襖を開き、雨戸を外して全ての窓を開けると、涼しい風が一気に通り抜けて行った。
通りに面した10畳の部屋は、祖父の書斎のようで、書庫よろしくたくさんの本棚が並んでいた。
祖父の心の師匠である永井荷風はもちろん、夏目漱石、森鴎外、坪内逍遥などの文学作品、江戸川乱歩や横溝正史に、エドガー・アラン・ポーやアガサ・クリスティーなどのミステリー小説も多い。
窓に面して置かれた存在感のある文机の上には、何冊もの原稿用紙と本が重ねられていた。
「小説でも書いていたんですかね。」
「いやあ…、そういう話は聞いたことがないですけどね。でも自叙伝でも書いたらどうですかって進めたことはありますよ。人様に見てもらうような人生じゃないって笑っていましたけど。」
蔵之介は、丸い煎餅布団の上に胡坐をかき、傍に転がっていた万年筆を拾い上げた。
開いた窓から雲ひとつない青空が広がっている。
ザワザワとした木々の擦れる音を聞きながら、生き急ぐように駆け抜けてきた日々が頭の中に浮かんでは消えた。
何を目指すわけでもなく、ただひたすら、滝の如く流れ落ちる時間を受け入れる毎日。
休み少なく働き、金を稼ぎ、比較的良いマンションに住んで、車も買った。
ときどきの休みはどこに行く気もせず、合コンで知り合った女から来たメールを思い出したように返してみる。
出逢いがないわけではない。何度か食事をするうちに深い付き合いに発展することはよくあった。
だが、急な仕事でデートを直前キャンセルする羽目になり振られることもよくあった。
・・・それが、蔵之介の日常だった。
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
「あ、明地あけちさん。」
不意に声がして我に返ると、窓際に立っていた白澤氏が窓から身を乗り出していた。
「ああ、白澤さん。……――あら。」
蔵之介が白澤氏の横から顔を出すと、窓の下にいた淡い紫色の着物を着た女性は、驚いたように日傘を下ろし、軽く頭を下げた。蔵之介も釣られるように頭を下げる。
「富士見坂にある“ふじみ荘”の大家さんです。この近くのご自宅で着付け教室をなさっているんですよ。」
白澤氏は口早に紹介すると「金鳳亭さんのお孫さんです。」と窓の下にも伝えた。
明地と呼ばれた女性はさらに驚いたように口に手を当て、今度は深々と頭を下げた。
「それは・・・、ご愁傷様でした。金鳳亭さんには色々とお世話になりまして。」
「いえ、こちらこそ祖父がお世話になりまして。」
蔵之介が身を乗り出すようにして返すと、明地夫人はしばらく眩しそうに蔵之助を見上げていたが、「嗚呼、金鳳亭さんと、よく似ていらっしゃるわ。」と静かに笑った。
「では白澤さん、あとで…15時過ぎるけれど、お伺いするから。」
「ええ、お待ちしております。」
明地夫人は着物によく似合う真っ白な日傘を差すと、カランコロンと軽やかな音を立てて遠ざかって行った。その姿が角を曲がると、白澤氏は窓を閉めた。風が止まるだけで温度が急に上がったように感じる。
「富士見坂というのは、富士山が見えるんですか?」
「ええ、今はマンションが建ってしまって半分ほど見えなくなっているんですが、冬の朝は特に綺麗に見えますよ。」
蔵之介は万年筆を机の上に置いた。『F坂の殺人』と見たことがあるようなタイトルが原稿用紙に殴り書きされている。
「“ふじみ荘”もかなり古い物件で、明地さんのご主人がご存命のときに、建て替えの話も出たんですが、安く借りたい人もいるだろうということで今もそのままなんです。」
「ああ、今はお独りなんですか?昔はさぞかし美人だったんでしょうね。あ、いや今も美人ですけど。」
軋む階段を降りながら蔵之介が言うと、白澤氏はわざとらしく声を潜めた。
「明地さんって・・・父の初恋の人なんです。」
不動産屋に着いた時、最初に対応してくれた年配の男の顔が思い浮かぶ。
白澤氏は笑いを含む口調で続けた。
「ご主人が亡くなる前はほとんど関わりなかったんですが、お独りになってからはご自身で動かざるをえないので、うちにも頻繁に来るようになったんです。
だから、明地さんが来る日には、必ず父は店にいるんですよね、お気に入りのネクタイをつけて。」
蔵之介は笑った。
「ああ、だから今日も店にいらっしゃったんですね。まあ、初恋っていうのは、実らないからこそ、いつまでも甘い思い出ですから。」
・・・初恋。
あの女の艶かしい笑顔が思い出される。祖父と一緒に柱の影からひょいと顔を出しそうで、思わず部屋の中を見回すと、年代物の柱時計が目に入った。ここを訪れてもう1時間も経っている。
釣られて時計を見上げた白澤氏は慌てて自分の腕時計を覗き込んだ。
「ああ、もうこんな時間ですね。お忙しいのにすいません。」
「いやいや、久し振りにゆっくり過ごせました。20年振りに祖父に歩み寄れたような気がして楽しかったです。」
店先のガラス戸から見える外は、うんざりするほど良い天気だ。
蝉の大合唱に、駆け回る子供たちの甲高い笑い声が響いた。
「では、ご検討いただいて・・・」
言いかける白澤氏を制するように、蔵之介は首を振った。
「もう決めました。白澤さんには長い時間お付き合い頂いたのに申し訳ないんですが…。」
白澤氏は蔵之介の言葉を理解しようと、何度か目を瞬いた。
「と、おっしゃいますと・・・?」
「誰にも売らず貸さず。この店で、古道具屋をやろうと思います。」
蔵之介は、声を失う白澤氏の横を通り、店に下りると、並んだ古道具を眺めた。
白澤氏はしばらく固まっていたが、やがて嬉しそうに笑みを零すと、蔵之介の後を追って古道具の前に並んだ。
「古道具の金鳳亭復活ですか?」
「いや、祖父のやり方を引き継げるわけじゃないから、店の名前も変えようと思います。そうだなぁ・・・――蔵之介からクラをとって、古道具のボンクラ堂とか。」
20年前のあの日、祖父に将来の夢を聞かれた蔵之介は「良い大学にいって、良い会社に就職する」と答えた。
すると祖父は「将来の夢がそんなチッポケとは、とんだボンクラだよ。蔵坊のクラはボンクラのクラに違いねえ」と呆れたように言った。
店の名前に、白澤氏は笑った。
「ボンクラって言葉、金鳳亭さん、よく使ってましたね。」
「口は悪いですからね、愛情のある罵倒ってやつかと。」
――ニャオン・・・
蔵之介の言葉に賛成したように、どこかで猫の鳴き声がした。
スポンサードリンク