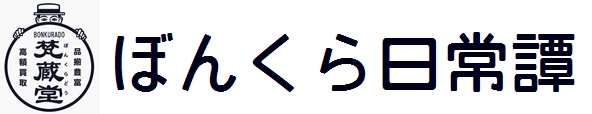賑やかな一団…主に賑やかだったのは風間ひとりだが、彼らが去った後の店内は妙に薄暗く、シンと静まりかえっていた。
そして店の奥の居間には女がいた。
祖父の恋人だったと思われる女が、20年前のあの時と変わらぬ姿で。
「あんたは・・・―― 何者だ・・・?」
「猫よ、彼も言ってたでしょ。」
脳みそに沁み込むような声、気だるげな仕草に、喋り方。
「俺には人間に見える。」
「金ちゃんもそうだったみたい。」
「金ちゃん・・・?」
「アンタのおじーちゃん。金鳳亭の金ちゃん。」
蔵之介はおそるおそる居間に上がると、ちゃぶ台を挟んで女の向かい側に胡坐をかいた。
「爺さんの恋人だったのか?」
女はけらけらと笑った。
「そりゃ、金ちゃんは良い男だったけどもさ。猫と人じゃ、恋に落ちるのは難しいもの。」
「でも俺が『新しい恋人?』って聞いたら『そうだ』って言った。」
「可愛い蔵坊をからかったのよ。あとは嬉しかったから。」
女は小さな仏壇に飾られた写真をちらりと見た。
「嬉しかった?」
「アタシが見えたこと。周りの人にゃ猫にしか見えないからさ。アンタの目で同じように見えたことが、嬉しかったんだよ。
アンタが帰ったあとにね、『やっぱり離れてたって血は繋がってやがるな』なんて笑ってたもの。」
幼い蔵之介が女を見て「おじいちゃんの恋人?」と訪ねた時、
祖父が少し驚いた顔をしたのをボンヤリと思いだした。
蔵之介も、女の視線を辿り、祖父の写真を見る。
まだ祖父が会社役員だった頃に、家族全員で撮った写真だ。
「あんた、名前は?」
「お福。」
「爺さんがつけたのか?」
「ううん、根津遊郭の姐さんにつけてもらったの。花紫って綺麗な姐さんでね、坪内っていう作家のセンセに貰われちゃったけど。」
蔵之介の頭の中では、根津という場所と遊郭という響きがあまりにもかけ離れていて、根津遊郭の根津がいわゆるこの地域の根津を示しているのだと理解するのに時間を要した。
ゆえに、お福の言う「坪内という作家のセンセ」が、教科書によく出てくる文豪、坪内逍遥であることまでは頭が回らなかった。
「根津遊郭?根津のあたりに遊郭があったのか?」
「蔵坊アンタ、そんなことも知らないの?・・・まあ、当然か。今では面影すらもないし。結構大きな遊郭だったんだけど、明治の頃にねえ、洲崎に移転したのよ。」
「お福さん、蔵坊はやめてくれないか。もういい大人なんだから。」
「お福でいいわよ。いいじゃない、蔵坊。ああ、蔵ちゃんでもいいわね、風間って馴れ馴れしい彼が呼んでたみたいに。いい大人もなにも、アタシからすりゃ、金ちゃんだって子供みたいなもんよ。」
蔵之介の目には、まだ30前後に見える女だが、話を聞いていれば、明治の頃100年以上も前から、この土地に住んでいるということだ。
蔵之介の心を読んだように、お福はくつくつと笑った。
「そーよ、産まれてもう130年になるかな。今じゃ、谷中銀座を仕切ってるトラジロウも、よみせ通り仕切ってるキンジも、この辺りを仕切ってるテラスケも、皆アタシの子供やら孫やらだもの。」
「そういうの、化け猫とか猫又とか言うんじゃないのか?」
「あはは!ホント、金ちゃんと同じこと言うんだから!まあ、なんだっていいじゃない。この家に金ちゃんが帰ってきた気がして、わくわくしてんのよ。」
お福は、のそりのそりと四つん這いに蔵之介の方に歩むと横に座り、しな垂れかかった。
触れた部分がじんわりと温かく、金木製のような甘い香りが鼻腔を擽る。
「俺は、爺さんのように立派な人間じゃないよ。がっかりしない内に出て行った方がいいんじゃないか?それに、この古道具屋は金鳳亭じゃなくて、梵蔵堂になるんだ。」
蔵之介はお福を押しのけると立ち上がった。
「知っているわ。“蔵之介のクラはボンクラのクラの違いねえ”ってね。だから梵蔵堂。店の名前を変えようと、内装を変えようと、金ちゃんはアンタの心に棲みついてんのよ。…ああそうだ。」
何かを思い出したように、お福は気だるげに立ちあがると、幼い蔵之介の心に刻まれた艶めかしい笑いを浮かべて、手招きした。
「ねえ、いらっしゃいよ。二階の住民にはまだ逢ってないんでしょう?」
「・・・・・・。・・・二階の何?」
「二階の住民よ。金ちゃんがこの家を買い取る前から棲みついている古株なの。」
垂直に突っ立ったまま口を開けた蔵之介を、お福は一層可笑しそうに眺めた。
そして店の奥の居間には女がいた。
祖父の恋人だったと思われる女が、20年前のあの時と変わらぬ姿で。
「あんたは・・・―― 何者だ・・・?」
「猫よ、彼も言ってたでしょ。」
脳みそに沁み込むような声、気だるげな仕草に、喋り方。
「俺には人間に見える。」
「金ちゃんもそうだったみたい。」
「金ちゃん・・・?」
「アンタのおじーちゃん。金鳳亭の金ちゃん。」
蔵之介はおそるおそる居間に上がると、ちゃぶ台を挟んで女の向かい側に胡坐をかいた。
「爺さんの恋人だったのか?」
女はけらけらと笑った。
「そりゃ、金ちゃんは良い男だったけどもさ。猫と人じゃ、恋に落ちるのは難しいもの。」
「でも俺が『新しい恋人?』って聞いたら『そうだ』って言った。」
「可愛い蔵坊をからかったのよ。あとは嬉しかったから。」
女は小さな仏壇に飾られた写真をちらりと見た。
「嬉しかった?」
「アタシが見えたこと。周りの人にゃ猫にしか見えないからさ。アンタの目で同じように見えたことが、嬉しかったんだよ。
アンタが帰ったあとにね、『やっぱり離れてたって血は繋がってやがるな』なんて笑ってたもの。」
幼い蔵之介が女を見て「おじいちゃんの恋人?」と訪ねた時、
祖父が少し驚いた顔をしたのをボンヤリと思いだした。
蔵之介も、女の視線を辿り、祖父の写真を見る。
まだ祖父が会社役員だった頃に、家族全員で撮った写真だ。
「あんた、名前は?」
「お福。」
「爺さんがつけたのか?」
「ううん、根津遊郭の姐さんにつけてもらったの。花紫って綺麗な姐さんでね、坪内っていう作家のセンセに貰われちゃったけど。」
蔵之介の頭の中では、根津という場所と遊郭という響きがあまりにもかけ離れていて、根津遊郭の根津がいわゆるこの地域の根津を示しているのだと理解するのに時間を要した。
ゆえに、お福の言う「坪内という作家のセンセ」が、教科書によく出てくる文豪、坪内逍遥であることまでは頭が回らなかった。
「根津遊郭?根津のあたりに遊郭があったのか?」
「蔵坊アンタ、そんなことも知らないの?・・・まあ、当然か。今では面影すらもないし。結構大きな遊郭だったんだけど、明治の頃にねえ、洲崎に移転したのよ。」
「お福さん、蔵坊はやめてくれないか。もういい大人なんだから。」
「お福でいいわよ。いいじゃない、蔵坊。ああ、蔵ちゃんでもいいわね、風間って馴れ馴れしい彼が呼んでたみたいに。いい大人もなにも、アタシからすりゃ、金ちゃんだって子供みたいなもんよ。」
蔵之介の目には、まだ30前後に見える女だが、話を聞いていれば、明治の頃100年以上も前から、この土地に住んでいるということだ。
蔵之介の心を読んだように、お福はくつくつと笑った。
「そーよ、産まれてもう130年になるかな。今じゃ、谷中銀座を仕切ってるトラジロウも、よみせ通り仕切ってるキンジも、この辺りを仕切ってるテラスケも、皆アタシの子供やら孫やらだもの。」
「そういうの、化け猫とか猫又とか言うんじゃないのか?」
「あはは!ホント、金ちゃんと同じこと言うんだから!まあ、なんだっていいじゃない。この家に金ちゃんが帰ってきた気がして、わくわくしてんのよ。」
お福は、のそりのそりと四つん這いに蔵之介の方に歩むと横に座り、しな垂れかかった。
触れた部分がじんわりと温かく、金木製のような甘い香りが鼻腔を擽る。
「俺は、爺さんのように立派な人間じゃないよ。がっかりしない内に出て行った方がいいんじゃないか?それに、この古道具屋は金鳳亭じゃなくて、梵蔵堂になるんだ。」
蔵之介はお福を押しのけると立ち上がった。
「知っているわ。“蔵之介のクラはボンクラのクラの違いねえ”ってね。だから梵蔵堂。店の名前を変えようと、内装を変えようと、金ちゃんはアンタの心に棲みついてんのよ。…ああそうだ。」
何かを思い出したように、お福は気だるげに立ちあがると、幼い蔵之介の心に刻まれた艶めかしい笑いを浮かべて、手招きした。
「ねえ、いらっしゃいよ。二階の住民にはまだ逢ってないんでしょう?」
「・・・・・・。・・・二階の何?」
「二階の住民よ。金ちゃんがこの家を買い取る前から棲みついている古株なの。」
垂直に突っ立ったまま口を開けた蔵之介を、お福は一層可笑しそうに眺めた。
スポンサードリンク